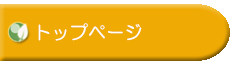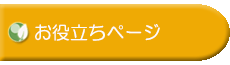さがみはら介護支援専門員の会 |さがみはらケアマネネットワーク
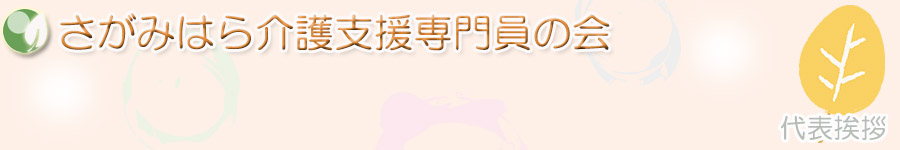
![]()
さがみはら介護支援専門員の会 代表挨拶

さがみはら介護支援専門員の会 代表 黒沢 愼五
令和5年度の通常総会において、さがみはら介護支援専門員の会代表に就任いたしました黒沢愼五と申します。
本会は、利用者本位の質の高い介護サービスが社会に提供される為に、介護支援専門員を中心に会員間で目指すべき方向性を共有し、情報の交換や連携を図る事を目的として平成13年より活動しております。
介護保険制度が始まった当初に比べ、私たちを取り巻く環境や業務内容は変化しておりますが、今もなお取り組まなければならない課題は介護支援専門員のなり手不足への対応です。
その原因としては、処遇や賃金の問題、介護支援専門員の高齢化、管理者要件が主任介護支援専門員になった事などもあります。
定年含め退職していく人が多いなか、介護支援専門員として働く事を目指す人が少ないのも嘆かわしい現実です。
現在働いている介護支援専門員が少しでも働きやすくなるように、また新たに介護支援専門員を目指す人たちの為にも、介護支援専門員の社会的地位の向上や処遇の改善などを、本会でも全力で取り組んでいきたいと考えております。
また、これらの事をはじめとして会員の皆様からの声や想いを、関係機関や他の職能団体と協議・連携していけるよう努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症はまさに災いですが、この災いからICTなどの活用が急速に進んだのも事実です。
現在の介護支援専門員不足から転じて、学生や子供たちの将来の夢にも「介護支援専門員」と言ってもらえる未来を創っていけるよう、本会としても精一杯取り組み続けてまいります。
その為には会員の皆様のお力添えが必要不可欠です。
より良い状況を目指して積極的に活動してまいりますので、引き続き、本会の活動に対してご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本会は、利用者本位の質の高い介護サービスが社会に提供される為に、介護支援専門員を中心に会員間で目指すべき方向性を共有し、情報の交換や連携を図る事を目的として平成13年より活動しております。
介護保険制度が始まった当初に比べ、私たちを取り巻く環境や業務内容は変化しておりますが、今もなお取り組まなければならない課題は介護支援専門員のなり手不足への対応です。
その原因としては、処遇や賃金の問題、介護支援専門員の高齢化、管理者要件が主任介護支援専門員になった事などもあります。
定年含め退職していく人が多いなか、介護支援専門員として働く事を目指す人が少ないのも嘆かわしい現実です。
現在働いている介護支援専門員が少しでも働きやすくなるように、また新たに介護支援専門員を目指す人たちの為にも、介護支援専門員の社会的地位の向上や処遇の改善などを、本会でも全力で取り組んでいきたいと考えております。
また、これらの事をはじめとして会員の皆様からの声や想いを、関係機関や他の職能団体と協議・連携していけるよう努めてまいります。
新型コロナウイルス感染症はまさに災いですが、この災いからICTなどの活用が急速に進んだのも事実です。
現在の介護支援専門員不足から転じて、学生や子供たちの将来の夢にも「介護支援専門員」と言ってもらえる未来を創っていけるよう、本会としても精一杯取り組み続けてまいります。
その為には会員の皆様のお力添えが必要不可欠です。
より良い状況を目指して積極的に活動してまいりますので、引き続き、本会の活動に対してご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
▼さがみはらケアマネネットワーク会則・入会申し込み ▼お役立ちページ ▼活動案内(当会ブログ)